12日、ユカリアが東証グロースに上場した。初値は公開価格の1060円を8%下回る975円を付け、981円で引けた。2005年に創業し、主に医療経営総合支援事業やシニア関連事業を行っている。全国にある赤字の病院や介護施設の経営・運営を一貫してサポートできる独自の体制が特徴。三沢英生社長が東京証券取引所で上場会見を行った。

―初値の受け止めは
現時点での評価だと思っているので、受け止める。まさにスタートラインなので、市場の期待に応えられるように、全力で邁進していきたい。
―上場の狙いや目的は
新型コロナウイルスが猛威を振るっていた時期に、コロナ専門病院を作ることを通じて、我々がやっているビジネスは極めて公的な存在ではないかと確信した。病院自体が公器なので、上場してオーナー企業から公器な存在になるべきだと感じた。
我々の世界観である「三方良し」を達成していくためには、今の規模ではかなり不足であり、ビジネスを拡大すると同時に、多くの仲間、これは医療従事者や介護従事者だけではなく、そのほかの業界や政府、官僚、自治体、メディアなど、色々な人の共感を得て、仲間を増やす必要があると考え、上場を決意した。
―最近グロース市場が少し低迷、横ばい傾向が続いているが、そういった市況を踏まえて今回のタイミングを選んだ理由は
上場を決意したのが2021年頃で、そこから最速のタイミングを証券会社のアドバイスで決めた。そのため、市場によって決めたというよりは、1番早いタイミングで上場した。上場市場のことは我々が特に何かできるわけではなく、我々がやるべきことは自分たちの事業を拡大し、仲間作りに徹底的にフォーカスすることだ。それによって株主にしっかりと還元できるようにしていきたい。
―上場するにあたって、特に力を入れてきたことは何か
来年の2月で20年になる会社だが、内部統制や監査体制といったところを極めて重視してきた。元々そういうことをやってきたが、これからより社会の公器になっていくための体制が自信を持ってとれた。事業に関しては、創業者の古川淳会長が作り上げたものから始め、どんどん進化してきている。そこに関しては何の問題もなく、さらに拡大していく。どこに出しても恥ずかしくない体制ができたと自負している。
―今後の売り上げで数値目標はあるか
今年の着地予想に関しては、売上高約199億円で、当期純利益が約20億円だ。来年以降に関しては、2月14日に発表するので、そこを見てほしい。
―中長期的な業績目標に関して
2025年2月14日に数字をしっかりと出していく。「非連続な成長を連続的にする」と私はよく言うが、上場は、まさに非連続の成長をしていくための1つの大きな武器になると思う。今までのオーガニックなグロースではない大きな成長をしていきたい。
―医療機関の支援の引き合い状況に関して
1番大きなインパクトがあるのは、福祉医療機構が行ったコロナ禍での緊急融資の返済が2025年から本格化する。これがかなりのトリガーになっており、地銀を含めて色々なところからの相談が、過去に見たことがないぐらいの量が来ている。もちろん我々の営業や実績で、当社の立ち位置が段々上がっているのもあると思うが、それでは説明できないぐらいの圧倒的な量と感じている。
引き合いの数は、倍というレベルではないぐらいの量で、困っている部分がたくさん増えていると感じる。昨年と比べ今年も増えているが、これがさらに来年は倍以上になることも予測でき、月を追うごとに増えてきている。
―コンサルやBPO企業とは違うという話があり、長期的な伴走や幅広い支援が競合とは違う特徴だと思うが、どうしてこれが可能なのか
これはまさに我々が誇る人材だと断定したい。西村祥一取締役を筆頭に、社内ではMAT(メディカルアシスタント)チームと言うが、まさに経営マインドを持った医師・看護師が社員として在籍している。それが最大の売りであり特徴であるが、それに加えて、例えばファイナンスに詳しい人間、人事労務に詳しい人間、データサイエンティストとかデータに詳しい人間。それから1級建築士を初めとする建て替えや修繕ができるような人材や卸、薬剤師など、様々な人材、プロフェッショナル集団がいることが、これを可能にしている。
―トータルで一貫して運営業務をしている企業はユカリアだけで、競合に同じようなビジネスモデルはないのか
病院に関しては、我々のような形でやっているところはないはずだ。BPOやコンサルティング企業などそれぞれのパーツでやっているところはあっても、トータルで一貫して運営業務をやっている企業はないと思う。
―人材が強みとのことだが、事業を拡大するにあたって、採用や育成に関して、何か課題などはあるか
グループも含めて800人程度の社員を抱えている。上場の狙いとも一緒だが、昨年ぐらいから一気に事業を拡大しようと、採用に力を入れている。今のところ我々のビジョンやミッションに評価をしてもらって、入社してくれる仲間たちが非常に増えており、今のところ採用活動で困っていることはない。本社が150、170、180人と増えてきて、来年も新卒を入れて30~40人ぐらい増員する予定だ。
―今後の高齢者施設の展開について
シニア関連事業は、大きく分けて、介護施設運営をしている「KURACI」と介護施設紹介をしている「あいらいふ」の2つがメインになっている。「KURACI」への質問だと思うが、12施設を運営している。しっかり現場に寄り添っていくという我々の大方針のなかでは、極めて重要な部分だ。今のところゆっくり増やしていく予定だ。
―高齢者施設の展開エリアは
今は関東が中心。だが、病院、定期療法に関しては北海道から沖縄まで展開しているので、同じように展開したいと考えているが、現時点ではまだ関東だけだ。
―介護保険制度も20年経って疲弊してきているが、上場を機に介護保険制度に関して何か取り組んでいくのか
診療報酬も含めて、どちらもそうだと思うが、地域医療構想に沿った病院も、病院の経営も求められるだろうし、介護施設の運営、経営でも求められると見ている。ここに関してはどちらも地域医療構想がベースになってくると予測している。
我々も、病院についても医経分離を提唱しているので、介護だけでなく、診療報酬も含めて、日々情報を収集してしっかり研究している。ヘルスケアの医療介護の部分で、しっかりと貢献したい。
そのために、関係省庁など様々なところと会話をして、情報交換や意見交換をしている。ありとあらゆるところと連携を深めたい。今日は仲間ということを1つのテーマに話しているが、全て仲間にしていくことが我々のテーマだ。
―患者の高齢化に伴って、外来の患者数減少や在宅志向など事業構造が変化しているが、病院経営のあり方、支援のあり方は変わっていくのか
基本的には国の目指している方向性に関して、我々は非常に寄与していると思っており、診療報酬に関しても日々情報収集している。次だけではなく、その次といった長期的な改定に対して経営判断をし、具体的なソリューションも用意しているので、病院と介護施設のどちらにも積極的に支援ができるだろう。国が目指す方向性に関しては強く同意し、軌を一にしてやっていく。
―今後のM&Aについてはどういった方向性があるのか
M&Aに関しては、病院経営サポートを軸に、医療系総合支援が祖業かつ中核事業で、未病・予防から終末期まで幅広いバリューチェーンを、今までも事業開発やM&Aでバランスよくやってきた歴史がある。その状況で、祖業で中核である医療系総合支援事業のところにシナジー効果があるものがM&Aの中心になってくるだろう。
一方で、幅広いバリューチェーンを有しているので、ヘルスケアを超えていきなり違うことをやるつもりは一切ない。バリューチェーンのなかでやっていく。軸はやはり医療系総合支援になるだろうと考えている。
―ソーシャルビジネスとして、海外進出は何らかの方向性としてあるのか
海外に関しては、長期的には非常にやっていきたいが、国内でおよそ8000の病院があって、その7割が赤字、つまり5000ぐらいが赤字で、問題が山積している。介護もそうだが、そういう状況のなかで、我々が国内でやるべきこと、提携医療法人が24という数字を資料には出していて、もうすぐ公表するが、そこから数件、今年末にも増えてきている。まだ国内でやるべきことがたくさんあると思っているので、目先に関しては国内に注力していこうと考えている。
―社長が東京大学のアメリカンフットボール部の監督をしているが、業務上のメリットはあるか
(部名が)WARRIORSというが、私は教育者なので、卒業後の遥か長い人生で真に躍動するような優秀な人材を育成し、配置しているつもりだ。そういった人間が皆いわゆる有名どころの大企業に勤めていくが、次々と(当社に)入社してくる。これは私の影響力だと勝手に思っている。びっくりするぐらい元アメフト選手だらけになっているが、皆優秀な人材で、これは最大のメリットになっている。また、元東大のアメフト選手は色々なところにいるので、ネットワークという意味では、事業に直接良い影響があるだろう。ただ、メリットのためにやっているわけではなく、結果としていい関係ができている。
[キャピタルアイ・ニュース 北谷 梨夏]
よく読まれている記事
 2025年7月4日 デンソー5年・10年債:7年ぶりの年限に機会優先、希少なAAA
2025年7月4日 デンソー5年・10年債:7年ぶりの年限に機会優先、希少なAAA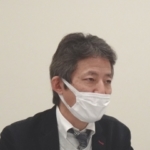 2022年3月3日 上場会見:イメージ・マジック <7793>の山川社長、ODPで究極の仕組みを
2022年3月3日 上場会見:イメージ・マジック <7793>の山川社長、ODPで究極の仕組みを 2025年1月16日 上場会見:フォルシア<304A>、賢い検索で旅行をスムーズに
2025年1月16日 上場会見:フォルシア<304A>、賢い検索で旅行をスムーズに 2023年4月3日 上場会見:Fusic<5256>の納富社長、AIとクラウドで宇宙も
2023年4月3日 上場会見:Fusic<5256>の納富社長、AIとクラウドで宇宙も 2025年8月22日 東武鉄道が5年債を準備
2025年8月22日 東武鉄道が5年債を準備





