11月29日、グロービングが東証グロースに上場した。初値は公開価格の4530円を23.62%上回る5600円を付け、5760円で引けた。コンサルタントが顧客内部でその事業責任者としてビジネスを推進するJoint Initiative(JI)型コンサルティングを得意とし、その過程で得られるノウハウを“型化”して作る各種SaaSを提供するクラウドプロダクト事業を手掛ける。輪島総介代表が2017年1月に設立した。田中耕平社長が東京証券取引所で上場会見を行った。

―上場初日の株価の受け止めは
5600円で初値が付いて、5760円で終値となっており、市場と市場の関係者に評価してもらえた。今後こういった市場の評価に日々晒されていくというところで身が引き締まる思いだが、株主の期待にはきっちりと応えていきたい。しっかりと成長していきたいので、長い目線で支援してもらいたい。
―JI型のコンサルティングは競合でも似たようなサービスがあるのか、参入障壁のようなものか
競合のなかにはなく、かなり特徴的なサービスになっている。我々が実施しているプロジェクトは、戦略性の高いものになっていて、外資の戦略ブティックと呼ばれる企業と競合する。我々の単価は、日本の企業や総合系のファームと比べると高い部類に属するが、外資のファームと比べると少しリーズナブルな価格で提供できる。
外資のファームは、ロイヤリティとして利益の一部を海外に支払うが、我々はそういった部分がなく、クライアントにその分を価格として価値を提供しているので品質はとても高い。外資の戦略コンサルと同等の人材がいて、そういったサービスを提供できるなかで、価格とをある程度抑え、長く付き合うパートナーとしてクライアントに認知されている。
外資でも総合系のファームや日本の国内のコンサルファームでは単価が少し低く、それによって品質があまり高くないといったところで、中核のテーマや大きな変革をともに行うパートナーと認識されてない側面がある。我々はそういったパートナーとして認識してもらい、入れている点でかなり特徴的になっていると見ている。
―JI型コンサルティングサービスの比率を高めていくとのことだが、現状ではどの程度の割合で、今後はどの程度までの拡大を目指すのか
現状では42%がJI型のコンサルティングだが、それを提供することによって顧客の粘着性が非常に高まり、長期で付き合うことができるので、この比率はできる限り高めていきたい。
理想としては100%、JI型の戦略コンサルティングサービスができるようにするのが狙いとなっている。
―クラウドプロダクト事業において、汎用性の高いノウハウを“型化”するとのことだが、どの程度の水準の知識を、例えば、特定のコンサルタントの属人的な知識や経験に基づくノウハウなどを、集合知化できるのか、その可能性と現時点で考えられる限界は
コンサルティング事業のなかでは、若手の工数をすごく使うが、型としては出来上がっているものは実際にはかなりあり、それが8つの領域のなかに散りばめられるが、そういったものは全部SaaSプロダクトとして提供できると考えている。
特定のコンサルタントの属人的な知識や経験という形でしか出せないようなものは、多分コンサルティングのなかに残る部分で、それを分析し、型に落とし込んでいくことで、若手のコンサルタントがかなり工数を使ってやっているようなものは、全部クラウドプロダクトに置き換えられる。
―クラウドプロダクト事業について、8つの領域のうち、現在手掛ける2領域を深掘りするのか。残り6つに対して新しいサービスを提供していくのか
まず、この2つについてビジネスをしっかり立ち上げていきたい。JI型を絡めたような、
クライアント企業と一緒にプロダクト開発をしていくモデルのような部分もあり、実際に使ってもらいながらビジネスとしての効果を出していく。コンサルタントではないが、カスタマーサポートよりは少し高度なサポートをしながら、そのモデルもプラスして報酬を得るビジネスモデルを考えていて、その辺りをきっちり作っていくことを、この2つのプロダクトを中心にしながら進めていこうと考えている。
そのビジネスモデルがある程度固まった段階で、ほかのプロダクトもどんどんリリースしていくことを考えている。まずはこの2つのプロダクトを、加えてもう1つぐらい出るかもしれないが、その辺りでビジネスモデルを作った後に、全体に広げていく。
―8領域全てでクラウドプロダクトを展開できるようになると、業務はどのような形に進化・変容するのか。また、収益構造に与えるインパクトについても聞きたい
全体的に展開することによって経営のプロセスのなかに織り込まれ、組み込まれていくことになると思っている。1つのクライアントが全てを使わなくても良いが、全部使うことによって、今までコンサルタントや高単価な人に依頼していたような作業を全部自動化できるようになる。そこから実際に人間がしなければならない価値を出していく作業については、カスタマーサクセスをさらに一歩深めたようなサポートのようなものを用意しながら提供していく。そうしたところを実施しながら事業価値を高めていく。
収益構造については、コンサルティング事業だけで見ても非常に高い収益性を出せると考えているが、クラウドプロダクトについても同様の収益性を最初から作っていけるモデルで展開していこうと思う。そういったものができた段階で、同じような利益率を担保しながら大きくしていくことを狙っているので、収益構造自体に大きくインパクトを与えるということはないだろう。
―海外展開は
今のモデルがある程度固まってきているので、早期に実施したい。ただ、コンサルティング事業はかなりローカル色の強いビジネスと見ており、ローカルで拡大していけるメンバーやパートナーと一緒になりながら拡大していくことになるので、そこを見つける動きをしていくと思う。
―株主還元の方針について改めて聞きたい
成長を追求して、キャピタルゲインで返していくことを考えているが、配当を含めたところも否定するものではないので、近い将来そういったところも含めて実施していくことは検討していく。
[キャピタルアイ・ニュース 鈴木 洋平]
よく読まれている記事
 2025年11月28日 イトーキ5年債:老舗オフィス家具大手の初回案件
2025年11月28日 イトーキ5年債:老舗オフィス家具大手の初回案件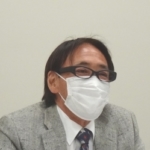 2022年6月27日 上場会見:坪田ラボ<4890>の坪田社長、 パイプラインに寄り添う
2022年6月27日 上場会見:坪田ラボ<4890>の坪田社長、 パイプラインに寄り添う 2025年9月12日 コーエーテクモHD<3635>:上場維持の野望、海外でも無双
2025年9月12日 コーエーテクモHD<3635>:上場維持の野望、海外でも無双 2025年9月11日 阪急阪神HD債:タイガース優勝直後に200億円、7年はぴちょんくんの内側
2025年9月11日 阪急阪神HD債:タイガース優勝直後に200億円、7年はぴちょんくんの内側 2025年12月5日 東急不HD37NC7劣後債:久々の事業会社ハイブリッド、ラベルの新規性
2025年12月5日 東急不HD37NC7劣後債:久々の事業会社ハイブリッド、ラベルの新規性





