3月27日、ZenmuTechが東証グロースに上場した。この日は初値が付かず、公開価格の1580円の2.3倍である3635円の買い気配で引けた。自社開発の秘密分散技術「ZENMU-AONT」を使った製品を開発・販売する。データを暗号化したうえで、複数の無意味なデータに変換して分散させ、個々のデータのみでは元データを復元・解析できないよう処理する。技術をOEM提供するほか、データを暗号化したまま加工・解析できる秘密計算技術も扱う。田口善一CEOが東京証券取引所で上場会見を行った。

―初値が付かなかった要因や感想は
我々への期待があり、特に第2軸の事業である「秘密分散ソフトウエア開発キット」では、メーカーとの付き合いによって当社の今の売上をはるかに超えることも想像でき、その点で評価されているのではないか。
酒井茂輝CFO:市場の評価として、需給を絞った点はもちろんテクニカルな要因にあるだろうが、非常にニッチな技術である一方で、適用領域の広さや成長ポテンシャルがある。今は1軸の「情報漏洩対策ソリューション」でコロナ禍以降のトレンドに乗っている。2軸の「秘密分散ソフトウエア開発キット」、3軸の「秘密計算ソリューション」は、成長余地のある領域と評価されている。
―海外展開を目指すのか
田口CEO:そうだ。既に進めている。
―調達資金の使途はエンジニアの採用か
酒井CFO:秘密分散の事業の第1軸である情報漏洩対策ソリューションは、事業としてはある程度黒字化でき、キャッシュが賄えている。これが当面の主力事業なので、営業やエンジニアの体制を強化していくが、自己資金である程度賄える。
一方で、第3軸の秘密計算には実用化に向けた課題があり、社会で使ってもらううえでも、もっと広めていかなければならない。今回のIPO資金を使って、エンジニアや、我々が自分たちで事業を興すのではなく、例えば、シンクタンクと協業する、製造業の会社とはサプライチェーン全体を通してデータを共通化して最適化するといった使い方を一緒に検討していく。どちらかといえば開発力と企画提案力、一緒に事業を立ち上げる営業企画のような人員も両方取っていきたい。
日本だけではそのような新しい試みが難しい部分もある。プライバシーデータや個人情報も含めて、データの有効活用は海外のほうが積極的な面があるので、現地企業や日系の海外法人と実績を作って、日本に持って帰る。そうして展示会出展や、米国に出張ベースの拠点を設ける形で、2~3年前から展開を進めている。
―技術や製品の海外からの反応は
田口CEO:米国の研究者からの発想で秘密分散が出てきた。AIもそうだが、AIは2回死んでいる。今は3度目のAIといって、やっと広がってきた。
秘密分散も1回か2回死んでいる。コロナ禍を経てやっと市場ができつつある。1回死んでいるなかで我々が特許を取っているので、競合相手がいないのは寂しい限りだが、逆に営業の展開次第では、ポテンシャルは無限大だ。そのやり方は非常に慎重に進めなければならない。
秘密計算は、海外の大手IT企業を含めて十数社が取り組んでおり、彼らと競合になっていくが、市場が全くでき上がっていない。日本も大手IT企業の研究所が進めているが、「呉越同舟戦略」で、市場を作っていかないことには、広まっていかないだろうと皆思っている。
今までは秘密分散の市場を作るのに大変で凄く時間がかかった。市場を作る喜びは、苦しいものだが経験上楽しんできたので、楽しんでいけるだろうとわくわくしている。
阿部泰久CMO:シンプルな技術で分散させ、2つでなく3つでも4つでも用途によって変えられ、サイズも変えられる。凄くシンプルな技術だが、データが集中的に管理されるので分散させたい顧客のニーズに合わせた時に、海外の人たちと話すと、「いろいろな分野に使える」と、非常に興味を持ってアイディアが湯水のごとく出てくる。そこから検証、実用化に結びつく形で会話が進んでいく。これは事業の「2軸」である秘密分散ソフトウエア開発キットの話だ。
酒井CFO:我々の技術は非常にニッチなもので、秘密分散の技術自体は学問領域として存在して、例えば、過去には日本の大手も取り組んでいる。一方で、我々が採用しているAONTの技術方式に取り組んでいるプレーヤーは世界的に見てもかなり少ない。
ブームが一巡、二巡して今は落ち着いた状態なので、この技術や製品を持っている企業は海外を見てもかなり少ない。ニッチなAONTのジャンルで、自分たちで改良・改善してきて、独自性は世界的に見ても多分少ない。
また、秘密分散の技術を持っていたプレーヤーは秘密計算に着目している。そのなかで見ても、我々の方式は、我々と経済産業省配下の産業技術総合研究所と共同で行っているレアなタイプだ。非常に珍しいので、秘密計算をやっている企業はほかにもあるが、独自性のある立場や技術となっている。
田口CEO:これからのストーリー付けはとてもセンシティブに進めなければならず大変だが、楽しみだ。セキュリティの文脈でそのまま持っていったら、多分潰される。今までの日本企業のテクノロジーは、グローバルで広まったものはほぼない。日本の産業を復活させるためにどのようにしていくか、大変だが頑張りたい。
―2軸の秘密分散ソフトウエア開発キット事業の海外戦略は米国か
米国が多い。欧州もある。
―エリアとしては欧州が多いのか
グローバル企業は米国が多いので、米国が多い。
―活動は展示会への出展か
出展も行っているが、グローバル企業とのアライアンスが徐々に進んできているので、直接のやり取りを始めた。
酒井CFO:2軸の海外展開について極端な言い方をしてしまうと、今、暗号化を適用している領域を我々の秘密分散に置き換える。そうすることでセキュリティがより高まる、使い勝手が良くなるといったメリットを提供していく。
米国は我々が出張拠点を設けて、そこで展示会や、現地のPC事業会社と話をすることで、米国が先行している。だが、例えば、台湾のような電子系ではソフトウエアではなくハードウエアに組み込んでいくような提案の初期の話し合いがある。シンガポールにはアジア太平洋の地域拠点があり、日系の進出先がある。まだ展開しきれていない部分があるが、地域を選ばずポテンシャルがあると考えている。
阿部CMO:グローバル拠点は酒井CFOが言った通りで、展示会などがいろいろある。あとは外資系企業の日本法人から問い合わせが入って、「面白いので海外の本社の人たちと会話させてほしい」という展開もある。最近は問い合わせがどんどん増えている。
―今はパソコン向けが1軸の情報漏洩対策ソリューションが事業の8割を占めるが、2軸の領域で、身近で展開可能な領域はどのようなものがあるか
田口CEO:無限大で、今はドローン関係がメーカーとしては最も多い。デバイス関係ではパソコンメーカー、スマホメーカーも始めている。あとはカメラメーカーも多い。
阿部CMO:監視カメラのようなもので、こうしものには非常に秘匿性の高い情報がある。盗難に遭いやすいので、ドローンやセキュリティカメラの市場が広がっている。
田口CEO:車載や家電もそうだが、2つのものが複合しない限りプログラムを実行する「EXEファイル」が動かないようにできる。セキュリティの文脈ではなくて、合体して初めてEXEファイルが動作する。合体して初めて車のエンジンがかかると思ってもらえれば良い。そういうものはエンタメ領域も含めてとても多い。「4人集まると雀卓が現れます」というエンタメでも良い。
逆方向から考えると、今までなかったテクノロジーなので、いろいろな分野に応用可能性がある。それを我々が優先順位を決めて取り組んでいくのが楽しみだ。
酒井CFO:重点ターゲットとしてはドローンや車載、AI監視カメラ。我々の技術の特色は、「分散してバラバラにする」。元のデータの塊よりも小さくすると言い換えられる。サーバーよりもPC、あるいはIoTデバイスのような保存領域が小さいもの、有線ではなくて無線の、通信回線が貧弱な状況でも我々の技術は適用できる。かつ、それをセキュアに保管したり、転送したりできるのが我々の強みを発揮できるフィールドと考えている。
田口CEO: BtoBtoC、コンシューマーレベルにも持っていけるテクノロジーとして、グローバル企業を巻き込んで話をしている。
―先の話だろうが、量子コンピューティングが広く社会実装されるようになった時に、技術でどう対応していくのか
阿部CMO:「耐量子性」の点をもう少し言えば、AES(Advanced Encryption Standard)という暗号方式は元々、耐量子性を持っていて、純粋にAESの処理だけでも耐量子性は高いと言われている。我々はその技術を使ってデータを暗号処理して、さらにデータを分散処理している。今は、我々は256bitのものを作っているが、もし今後さらに加速してくればそれを512bitに変えていくとか、そのような対応は十分にできる。
AESによる暗号処理でも70年後まで大丈夫だと言われている。ただ、そのうえで、さらにデータを分割して物理的に分散配置することにしているので、耐量子性では、一定の対応性があると見ており、PCの保護やいろいろな分野で活用が広がってくると思う。
田口CEO:一方では、量子通信の部分とコラボレーションできる話を進めている。
―株主還元の方針は
ストックビジネス、ロイヤリティとサブスクビジネスなので、ある程度固まってきたら株主には40~50%の配当をしていきたい。ただ、まだ累積損失があるので、これを一掃してからの話になる。
[キャピタルアイ・ニュース 鈴木 洋平]
よく読まれている記事
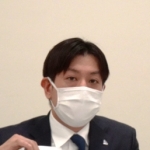 2021年6月24日 上場会見:アイドマHD<7373>の三浦社長、中小から大企業まで営業支援
2021年6月24日 上場会見:アイドマHD<7373>の三浦社長、中小から大企業まで営業支援 2025年12月19日 オークマ<6103>:多様な工作機械、注目度高いセクター
2025年12月19日 オークマ<6103>:多様な工作機械、注目度高いセクター 2025年7月18日 三井住友海上4本立て債:年度最大の2000億円
2025年7月18日 三井住友海上4本立て債:年度最大の2000億円 2023年7月28日 上場会見:GENDA<9166>の申社長、アミューズメントから隣接領域へ
2023年7月28日 上場会見:GENDA<9166>の申社長、アミューズメントから隣接領域へ 2023年6月28日 上場会見:クオリプス<4894>の草薙社長と澤CTO、心臓以外も修復
2023年6月28日 上場会見:クオリプス<4894>の草薙社長と澤CTO、心臓以外も修復





