~特別企画・IR担当者座談会~
■投資単位が下がると…
―この座談会の企画の検討過程で、東証から株式の売買単位を100株からもっと少ない単位に変更しようという話が出てきた。現時点ですぐに何かということはないだろうが、こういった動きが起こると、どういうことがありそうか。流動性や株主管理コストの上昇などいろいろなことが起きると想定できる。会社の方針というよりも個人的にどう考えるかというほうが答えやすいかもしれない
noteの鹿島氏:最低単位が引き下げられて、例えば、1株からでも売買できるという時に、発行体側からパッと思いつくことは、管理コストが増して、特に株主総会はオペレーションが難しくなるのではないかということ。一方で、一般論として最低単位が引き下げられ、いろいろな人が株を買えるようになったほうが良いのでメリットとデメリット両面ある。
ただ、前提として、今は1単元で100株というのが多いだろうが、その1単元を前提に株式数やオペレーションを設計しているのが現在の上場企業だと思うので、そことの接合をどうするかという事務的な問題はあるだろう。その点を無視すると一般論としては株が少額から買いやすくなるのは、流動性が増していろいろな個人が参入しやすくなり、個人が個別株に投資しやすくなるので良いと考える。発行体の側からすると既存の制度を軸に株数を決めているので、もし変わる場合はオペレーションを見直す必要がある。
―ここは皆さん同じような結論に収斂していくのか
グラッドキューブの財部氏:これは発行体側が自分たちで決めて良いというものなのか
―東証の口ぶりからすると一括で100株からを1株からにするという印象だったが。どういう制度設計なるかは、そこまで詰めてはいないかもしれないし、実現するかどうかもという点もあるかもしれない
グラッドキューブの財部氏:最初は小さい規模の証券会社から始まり大手でもやり出したのが、単元未満の株をミックスして少額から投資できるようにしている。それを投資家が手放した時に、変則的な株数で発行体が買い戻さなければならなかった経験がある。端数の単元株ではなく、十何株だけ引き取るような…。今後も発生するのであれば10株からの取引があってもいいとは思う。
アピリッツの永山氏:多分一緒ではないか。ステージによって望んでいるものが発行体側も違うので、例えば、自分の手間やコストが増えてしまうのはどこも一緒だが、小型株ではやはり入ってきてくれるのは嬉しい。
単元が低かろうが、まず興味を持って1歩踏み込んでくれる、どこかで売ってもらっても構わない。そういう意味では歓迎したい。ただ、プライムみたいになると、「それでやり取りされたらリソース的にもコスト的にも堪らないよ」というのは多分あるだろうが、それぞれのスタンスや置かれたステージで違うのではないか。当社ぐらいでは、逆にそれをやってくれると嬉しい。「知ってるけど買わないよ」、なぜかというと「そこまで出す気はないよ」という人が入ってきてくれたりするだろうし、それは良いと思う。
―渡邉さんはどうか
ユミルリンクの渡邉氏:特にどちらが良いというのはないが、アピリッツの永山さんと一緒で、中小型に関しては、実質的にまだ機関投資家もなかなか入って来られるレベルではない。それを考えると個人投資家に入ってきてほしい。
ただ、単元株の話があって、その金額を出すのであれば違うところに行ってしまうぐらいであれば、取得株単位で「少しであればちょっと持っても良いかな」みたいな人たちに保有してもらえるのは流動性の観点で良いのではないか。
他方、1株単位で持つ人は、おそらくいろいろな情報によって売買が激しくなるので、悪い面で言うと、ボラティリティが非常に高くなる可能性がある。メリットとデメリットがそれぞれあるので、会社ごとにどちらかを選べるのがベストだと思う。
オーケーエムの森川氏:個人投資家の裾野が広がることは当社としても歓迎すべきことだ。ボラティリティが高まるリスクはあるものの、流動性が向上することは喜ばしい。実際に始まってみての結果や、管理コストの影響などを考慮しながら、発行体として検討できることがあるのか分からないが、基本的なスタンスとしては前向きに捉えている。
■人的資本は厚めに
―上場市場の変更と非財務情報の開示について。上場市場を変えてステップアップしていく時に開示内容を充実させていくべきなのかという疑問が挙がっていた。非財務情報の開示の現状や今後の取り組みについて
オーケーエムの森川氏:非財務関連に関しては、義務化された有価証券報告書や、それに関連する決算説明資料などのIR資料にも掲載している。当社の事業は脱炭素に直結しており、例えば、アンモニアを燃料として航行する船舶向けのバルブや、将来的に液化水素運搬船で使用されるバルブなど、研究開発と製品開発を進めている。これらの取り組みは、確実にESGの「E」(環境)には貢献できると考えている。
一方で、人的資本や自社の工場・サプライチェーン内でのCO2削減に関しては、まだ課題が残っている。現在、第2次中期経営計画の策定に着手しており、中長期的なCO2削減目標や、人的資本に関する女性活躍や多様性の推進についても、企業価値の向上を目指して社内でも議論を進めている。この取り組みを単なる開示目的ではなく、しっかりと投資家に伝えていきたい。
アピリッツの永山氏:サステナビリティのページを作ってあるので、そこで開示している。事業的にはITと言っても結局は開発なので、労働集約型だ。ESGのEはやることが限られているが、当社は人が全てなのでソーシャルとガバナンスの点は、マスト開示で出しているもの以外でも、数値データをかなり出している。採用ページと遜色ないものにした。
人事系のデータは、女性比率や給与、平均残業時間など求人募集を出す際と同等の数値データなどを、IRのサステナビリティのページも同期を取って詳細に提示している。IRの観点からどうなのかというのは置いておいて、会社の求人で言っていることや、社内の方針で言っていること、IRで、ESGのソーシャルやガバナンスの情報に情報開示に差があるのではおかしいよねという趣旨で、サステナビリティのページに全て載せている。
noteの鹿島氏:当社は昨年が上場1年目で今年が2年目というところで日が浅いが、人的資本については今年の成長可能性資料で開示を行った。当社も人が資産なので、どれだけ競争力のある人材を育て生産性向上にどう取り組んでいくかということについて重点的に意思を持って人的資本の開示をしている。環境などには手が追いついていないが、経営という意味では人的資本は厚めに出している。
グラッドキューブの財部氏:当社も「サステナビリティ基本方針」をコーポレートサイトで開示している。非財務というと例えば、SaaSのチャーンレートや顧客に関する情報も含まれるとすれば、当初からKPIとして出している。ESGやSDGsなど、当社は元々女性役員・管理職比率が高いので、打ち出していくべきだと最初からやっていた。
ユミルリンクの渡邉氏:当社もITでSaaS系の会社なので、EというよりはSやGに関して開示している。そのほかは、具体的な人的資本などに関しても、少しぼんやりとした出し方ではあるが女性の比率など一般的なところは、有報の話もあるので開示している。
今年から統合報告書のライト版のようなものを開示しており、後程の議論であるかもしれないが、人的資本の話になると、採用やHRなどを統合的に考えなければならない部分があった。投資家向けのIR資料では、採用や社内の人に向けても作ったほうが良い。そのように取り組んで開示していく。
■SDGsからDEIへ
―ESGという言葉が出てきた。IPOの案件を見ていると、海外機関投資家からするとESGに配慮していることは投資の前提として見られていることを頻繁に聞く。また、それとは別にESGという概念自体が胡散臭いと言われることを見聞きすることもある。実際に海外機関投資家と話していてその辺りはどうなのか
ユミルリンクの渡邉氏:当社の場合ファンド系が多く、全般的にそうではないと思うのだが、ESG云々というのはけっこう少ない。
―脱炭素の話も出てきて、IT系の発行体では難しい部分があるかもしれない。最近ではDX支援を手がけつつ、「GXも一緒にやってみよう」という会社もあり、大手を中心に実証実験を行っているという話を聞く。GXはこれからの開示との関係でどう絡んできそうなのか。可能であれば製造系の森川さんに聞いてみたい
オーケーエムの森川氏:まずはスコープ1と2に関して、自社のCO2排出量を正確に算出することが重要だ。これに対応する体制を整えるのにもかなり苦労したが、一旦スコープ1と2までの排出量を算出できるようになった。ただし、スコープ3の算出となると、エクセルベースでは対応が難しいというのが実感としてある。
最近では、CO2排出量見える化サービスを提供するアスエネなどの企業からのアプローチが増えている。目標設定と併せて、CO2の算出や削減についても、太陽光発電やクリーンエネルギー由来の電力源を活用する方法が議論の中心となっている。最終的にはそのどちらかになってくるのではないかと話している。これは、投資家目線というよりも、当社が社是のなかで掲げる「地域社会に貢献する」に基づき、地球環境への貢献を会社として実現するための取り組みだ。
SDGsに対して懐疑的という話があったが、当社の役員が中国へ出張した際に、ジャケットにSDGsのバッジを付けていたところ、現地の人から「そのバッジは日本人しか付けていない」と言われたそうだ。この話からも、日本だけがSDGsへの関心が高まっていることが窺える。しかし、サステナビリティ、ESG、SDGsというテーマはどれも無視できない重要な課題であり、企業としても個人としても、中長期的に取り組むべきことだと考えている。
当社もSDGsやESGという言葉を使いながら、最近では「サステナビリティの取り組み」という表現にシフトしている。
アピリッツの永山氏:受け止め方や切り分けは難しい。実際に外部の機関投資家がESGやSDGsと切り分けて表現しているので、だから「それに合わせて対応しています」と言ったら怒られてしまうが、例えば、当社は事業を進めるなかで、人を大事にしないといけないので、女性の比率や退職率、障害者の比率がどうなっていて、こういう採用計画で、こういう教育をしますというのは、元々ESGのページで開示していた。しかし、それはESGにも出てくるし、CG報告書にもある。中計でどうやって育てていくのかというところにも出てくる。投資家からすると、やっていたことを切り分けて出しているからひょっとしたら「よく分かんない」みたいに思われてしまうのではないか。
実は全部繋がっていて、やっているほうとしては特段「ESGをやっている」と思って取り組んでいるわけではなく、やっていることがESGの切り口で切り取ってくると「こういう風にやってますよ」というもので、そんなに気にしている会社はないのではないか。全部少しずつ重複している。資料を作っていて思ったのは、「いやいや全部統一してくれ」ということだった。
地球全体としては環境に配慮しようというのがあり、特に欧州ではその意識が強いので、SDGsやESGを評価する機関がある。その機関は各社のサイトを見て評価する。ページが作られているか、必要な項目は開示されているのかというのがあるので、当社も将来評価してもらうために、サステナビリティのページを別で出した。ページがあるだけで、1回スコープが入る。せっかくやっているから評価されたいのでページを分けているが、なぜ分けているのかというと別に胡散臭くやるためではなく、そういう背景がある。森川さんの会社も作っているバルブ自体がESGで、二酸化炭素を減らす製品作りを考えると、発行体側はそれほど意識していないのではないか。
ただ、そういう盛り上がりを見せていただけたので、やれていることはこれ、やれていないことはこれというように切り口ごとに分けていく感じだと思う。
オーケーエムの森川氏:確かに当社もサステナビリティのページは日本語のみで公開しており、永山さんの言う通り、当社がこれまで取り組んできたことや今後の計画を「ESGとしてはこうです」と説明し、さらに「この項目はSDGsの17の目標のどれに該当します」といった形で整理している。他社でも同様の事例が多く見受けられる。現状としては、日本企業はそのような形式で網羅しておかなければならないという感覚がある。次の話に繋がるだろうが、日本の学生にとってはESGよりもSDGsという言葉のほうが共感されるのかなという感覚がある。
グラッドキューブの財部氏:個人的にSDGsと言う人は少なくなった印象がある。それよりもむしろDEI(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)のほうが使われて始めているのではないか。組織や社会において多様性を尊重し、すべての人々を包摂的な環境で受け入れ、多様な人材を活躍させることを重要視する考え方だ。すでに男女だけで区分けされることも減ってきていて、多様性やアイデンティが尊重されている。
アピリッツの永山氏:財部さんの言う通り浸透している。ESGのページのなかにもダイバーシティのことが書いてある。発行体としては企業価値を上げるのにやっているので、切り口毎に意識しているわけではない感じだと思う。
(後)に続く
よく読まれている記事
 2025年11月5日 財務担当に聞く:中国電力、トランジション・ファイナンスで脱炭素と財務安定両立
2025年11月5日 財務担当に聞く:中国電力、トランジション・ファイナンスで脱炭素と財務安定両立 2025年11月27日 サカタインクス<4633>:インキから化学マテリアル、海外の連携強化
2025年11月27日 サカタインクス<4633>:インキから化学マテリアル、海外の連携強化 2022年12月20日 上場会見:トリドリ<9337>の中山社長、インフルエンサー市場を広げる
2022年12月20日 上場会見:トリドリ<9337>の中山社長、インフルエンサー市場を広げる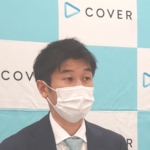 2023年3月28日 上場会見:カバー<5253>の谷郷社長、海外の熱量を高める
2023年3月28日 上場会見:カバー<5253>の谷郷社長、海外の熱量を高める 2025年12月24日 大和証券GをA+からAA-に格上げ(JCR)
2025年12月24日 大和証券GをA+からAA-に格上げ(JCR)





